
お気軽にご質問・ご相談ください
◆診療時間 9:30~13:00/14:30~19:00
◆休診日 木曜日・日曜日・祝日 土は17:00迄
〒180-0022 東京都武蔵野市境1-5-3 1階
親しらず
親しらずは、第三大臼歯(3rd molar)、智歯(wisdom tooth )、8番(中切歯から数えて8番目の歯)と呼ばれます。10代後半から20代前半に口腔内に顔を出す場合が多く、また全く生えない場合もあります。顎の成長がほぼ終わった状態の所に生えてくるため、スペース不足の為、様々な問題をおこすことがあります。
親しらずはこんな歯
親しらずは、最後に生えてくる歯であるため、生える場所が十分にない場合には、生えてこれない状態「 埋伏智歯」や一部顔を出している状態「半埋伏智歯」となります。また、歯が生える過程で隣在歯(第二大臼歯)を押し、結果として歯並びに影響を及ぼすこともあります。一部でも歯冠が口の中に現れたらレントゲンによる確認をした方がよいでしょう。
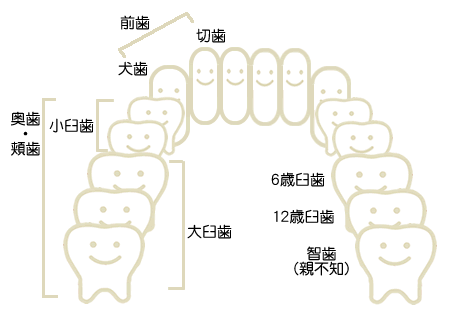
親しらずの生え方
①上下の親しらずがしっかりとかみ合っ��ている状態:正常な生え方です
②斜めあるいは水平に生えた状態:多くの場合、トラブルを起こします
③骨の中に埋まった状態:場合によっては歯冠部に嚢胞を作ることがあります


半埋伏智歯・水平埋伏智歯の引き起こす症状
親しらずは一番奥に生えてくる歯であるため、歯垢が溜まりやすく、唾液も届きにくいため むし歯や歯周病のリスクが高い歯です。
①智歯周囲炎 親しらずの周りの歯肉や骨の炎症です
②第二大臼歯のむし歯
③第二大臼歯を圧迫・移動させ歯並びに影響する

親しらずの予防的抜歯
親しらずが存在することによる将来的なリスクを考慮して抜歯をする場合があります。
抜歯をいずれするであろう場合に、若いうちに親しらずを抜いた方がよい理由には次のようなものがあります。
①若い時の方が傷の治りがよい
②親しらずによって生じる問題(歯を押す、隣の歯のむし歯、骨の炎症など)が少ないうちにすむ
③骨に柔軟性があり抜きやすい
④歯と骨の一体化(歯根膜の石灰化)がない
⑤全身状態の問題が少ない
抜歯後の症状
抜歯に伴う症状として次のような事が起こり得ます。
・歯を抜くという行為は創を作っているという側面もありますので、抜歯に伴い炎症を生じます。
術後3日目ぐらいが腫れと痛みのピークとなります。
・まれに下顎の親しらずの抜歯に際して、智歯と下歯槽神経(下顎神経の枝)が近接している場合に傷つく場合があります。唇や口唇にしびれ感がでることがありますが、通常数カ月で治ります。
・まれに内出血により、黄斑がでることがあります。2週間程度で消失します。
・上顎では耳や鼻の方へ、下顎では喉の方へ腫れや痛みが広がりやすいです。
下顎水平埋伏智歯の抜歯の流れ
1)術前の診査診断
レントゲン写真(パノラマX線撮影やCT撮影)、全身状態(血圧や糖尿病、血液の状態など)を確認します。
2)麻酔
局所麻酔を行います。同時に血圧やSpO2、脈拍などを測定します。
3)粘膜の切開
粘膜にメスを入れ、親しらずがみえる状態にします。
4)骨の切削
必要に応じて、歯冠を覆う骨を切削します。
5)歯の分割
必要に応じて歯冠、歯根を分割します。
6)歯の脱臼
ヘーベル(エレベータ)の梃子作用、楔作用、回転作用を利用して歯を顎骨から脱臼、分離させます。
7)歯の抜歯
鉗子で脱臼した歯を口の外に取り出します。
8)炎症部位の掻爬
抜歯窩の確認、炎症している不良肉芽や嚢胞を除去します。骨に尖った場所がある場合には整えます(骨整形)。
9)縫合
傷口を糸で縫います。
10)止血確認
止血、バイタルサインが安定していることを確認後、帰宅していただきます。
11)投薬
痛み止め(鎮痛剤)、化膿止め(抗生物質)などの薬を飲んでいただきます。蕁麻疹などが出た場合には服用を中止してください。
12)抜歯後確認
抜歯後、次の日に創口の確認、1週間から10日後に抜糸を行います。