
お気軽にご質問・ご相談ください
◆診療時間 9:30~13:00/14:30~19:00
◆休診日 木曜日・日曜日・祝日 土は17:00迄
〒180-0022 東京都武蔵野市境1-5-3 1階
インプラント
インプラントは、顎骨に直接チタン製の人工歯根(インプラント体、フィクスチャー)を埋め込み、その上に上部構造体(クラウンやアタッチメント)を作る治療法です。第二の永久歯とよばれる場合もあるインプラントによって天然歯のようなかみ合わせを回復します。
インプラントの構造
インプラントはシステムによって多少ことなりますが、次のようになります。
① インプラント体(フィクスチャー):天然歯の歯根にあたる部位です
② アバットメント:インプラント体と上部構造体を結ぶ土台となる部位です
③ 上部構造体:人工歯です
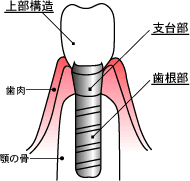
治療手順
① 診査・診断
口腔内診査(各種検査、模型、レントゲン、CT)、全身状態の確認など
② 埋入手術(1次オペ)
インプラント体を顎骨に埋入します。
③ 経過観察
手術部位の治癒を待ちます。インプラント体と骨が接合するまで3、4か月かかります。
④ 粘膜貫通部の手術(2次オペ)
インプラント体にヒーリングアバットメントを取り付け、粘膜貫通部を整えます。
⑤ 上部構造体の印象採得
型取りを行います。上部構造体を製作します。
⑥ 上部構造体の取り付け
人工歯を取り付けます。
⑦ 経過観察
定期的に状態を確認し、必要に応じて清掃や調整を行います。



生体親和性
インプラント体は骨と接合(オステオインテグレーション)する性質のあるチタン製です。生体親和性が高く、安全な材料です。骨折時に用いるスクリューや人工関節の材料でもあります。
対象となる方
基本的には歯をうしなった全ての患者さんが対象となります。下記に示すような方の治療は慎重な判断が必要になります。
(1)骨の状態
インプラント治療は顎骨にインプラント体を埋め込む手術を伴うため骨の状態が特に重要となります。埋入予定部位の骨量不足や形態不良、骨粗鬆症、未成年者(顎の成長が終っていない年齢)下歯槽神経や上顎洞の位置、上顎洞形態や炎症の有無など骨の状態を確認します。
(2)喫煙
タバコは歯周病の最大のリスク因子とされています。
(3)糖尿病
糖尿病の場合にはインプラント体と骨が接合しない場合があります。
(4)重度歯周病
コントロールできていない歯周病がある場合にはインプラント周囲組織炎・周囲炎を発症する場合があります。
(5)歯ぎしり、噛みしめ
歯ぎしりや噛みしめ、ウェイトトレーニングなど歯に過度な負荷がかかる場合には、マウスピースの使用などで力のコントロールが必要となります。
(6)開口量不足
外科手術を行うため、最低限必要な開口量が存在します。
術後トラブル
インプラント治療はインプラント体(フィクスチャー)の埋入手術を伴います。外科手術であるため下記のようなトラブルを生じる場合があります。
(1)痛み
外科手術を伴いますので、創口の痛みが伴います。鎮痛剤でコントロールします。
(2)腫れ
抜歯手術と同じような腫れを伴います。2、3日後をピークに徐々に落ち着いてきます。
(3)内出血・出血斑
希に出血斑を生じる場合があります。2週間ほどで消失します。
(4)上顎洞炎
上顎臼歯部ではインプラント体と上顎洞の距離が近く、炎症が波及する場合があります。
(5)初期脱落
骨とインプラント体が接合することなく、脱落してしまう場合があります。この場合にはインプラント体を除去して、骨の治癒をまってから再度埋入手術を行います。
(6)セラミックのチッピング
インプラントはしっかり噛めるため、瞬間的に強い力がかかった場合や歯ぎしりなどによって上部構造体として使用したセラミックが破折する場合があります。歯ぎしりや噛みしめることの多い仕事、ウェイトトレーニングをする方には、マウスピース(ナイトガードやスポーツマウスガード)の使用をしていただきます。
(7)下歯槽神経麻痺
下顎臼歯部では下歯槽神経が近い為、診査・診断の段階でCTを用いて距離や位置を確認して避け手術を行います。神経走行はCT上に現れない細いものもあり麻痺の可能性もあります。麻痺がでてしまった場合にはインプラント体を引き上げたり、神経を賦活化する薬の服用をしてもらったりして対処します。
(8)内ネジのゆるみ
インプラント体と上部構造体を取り付けているネジが緩む場合があります。ネジのゆるみはインプラント体の脱落や破折の原因となります。カタカタした場合にはなるべく早くネジをしめにきてください。
(9)インプラント周囲組織炎・周囲炎
インプラントにも歯周病のような症状がでる場合があります。日頃の歯磨きと定期的な歯科医院でのケアが重要です。
メインテナンス
補綴装置の生存率は平均 ブリッジで8年50%、インプラントで10年95%とする報告があります。インプラントの生存率はブリッジよりも高いものですが、長く使用するためには3から6カ月おきの定期的なメインテナンス、最低年1回のレントゲン撮影が重要です。
費用
すべて自費診療となります。使用するシステムや追加される手技によって費用が変わります。